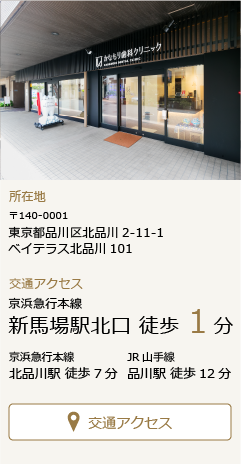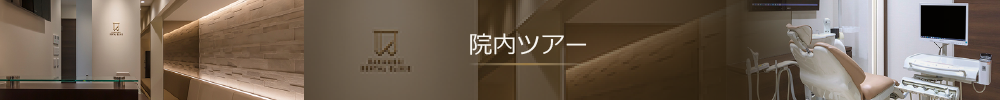矯正歯科治療は、適切な診断に基づき、適合する治療方法を選択し、信頼性のある技術で計画的に進めることで、予測性と質の高い結果が期待できます。しかしながら、医療行為である以上、身体への予期せぬ反応や治療上のリスクが生じる可能性はゼロではありません。本ページでは、矯正治療中に想定されるリスクや副作用について、事前に知っておいていただきたい内容を整理しています。
なお、これらの情報は、必要以上に不安を煽ることを目的としたものではありません。むしろ、リスクを理解し、適切な判断と対処ができるよう備えることで、安心して治療に臨んでいただけることを目指しています。
矯正治療にともなう主なリスク・副作用
※以下に記載する内容は、すべての方に必ず起こるものではなく、個人差があります。
1. 装置による違和感・粘膜への刺激
矯正装置を装着した直後は、痛みや異物感が生じることがあります。これは装着または調整後数時間から始まり、2~3日をピークに徐々に軽快することが一般的です。ワイヤーやフックが粘膜に接触し、口内炎などを引き起こすこともありますが、薬の塗布や調整で対応可能です。
2. 歯の動きに伴う痛み
歯が動く際に鈍い痛みを感じることがあります。痛みの感じ方には個人差があるため、調整の強さを調整したり、痛みの出にくい装置を用いたりすることで軽減できます。
3. 治療期間の延長
歯の動き方には個人差があるほか、装置の使用状況や通院頻度など患者様の協力度によって治療期間が変動することがあります。技術の進歩により全体の期間は短縮傾向にありますが、想定より長引く可能性はあります。
4. 装置周囲の虫歯リスク
装置が歯磨きを難しくさせ、プラークがたまりやすくなることで虫歯や歯周病のリスクが上がります。定期的なプロケアと丁寧なセルフケアが必要です。歯の移動により隠れていた虫歯が露出する場合もあります。
5. 歯肉炎や歯周炎の可能性
磨き残しにより歯肉が炎症を起こし、歯肉炎や歯周病につながることがあります。継続的なブラッシング指導と清掃が予防につながります。
6. 治療中のホワイトニング制限
使用する装置の種類によっては、矯正治療中にホワイトニングができないことがあります。特に表側矯正では制限が大きく、マウスピース型であれば対応可能です。
7. 歯根吸収のリスク
矯正力によって、歯の根の先端が短くなる「歯根吸収」が起こる可能性があります。これは正常な範囲の治療でも発生することがあるため、定期的なレントゲン検査で経過を確認します。
8. 過度な力による歯のダメージ
強すぎる矯正力や咬合力が特定の歯に集中すると、歯根膜が損傷し、重症化すると歯を失うリスクもあります。適切な力の調整や咬合管理が必要です。
9. 顔貌や口元の予期せぬ変化
治療目標や方法の選定によって、意図しない口元の変化が生じる場合があります。事前に顔貌への影響を想定し、慎重に治療計画を立てる必要があります。
10. 歯ぐきの後退・ブラックトライアングル
歯ぐきが下がったり、歯と歯の間に空隙ができる「ブラックトライアングル」が生じることがあります。審美的な問題となる場合には補正を行うこともあります。
11. 骨性癒着による歯の移動障害
外傷歴のある歯などが骨と癒着していると、期待する歯の移動ができないことがあります。この場合は専門医との連携が必要になります。
12. 歯髄への影響(充血・壊死)
稀に、歯の移動によって神経が障害され、歯髄充血や壊死を引き起こすことがあります。こうした場合には神経治療が必要になることがあります。
13. 金属アレルギー
装置に含まれる金属によって、アレルギー反応を起こす可能性があります。症状が現れた際は、アレルギー対応の装置に変更します。
14. 顎関節症の発症
かみ合わせの変化が顎関節に負担をかけ、音が鳴る、開けづらい、痛みが出るなどの症状を伴うことがあります。必要に応じて顎関節の治療を行います。
15. 治療計画の変更
装置の使用状況や協力度、口腔筋機能訓練(MFT)の実施状況などによっては、当初の治療計画の見直しが必要となることがあります。
16. 健康な歯を抜歯する可能性
歯列とあごの大きさの不調和などにより、治療上やむを得ず健康な歯を抜歯するケースもありますが、できる限り状態の悪い歯を選ぶなど配慮します。
17. 抜歯後の痛み・腫れ
抜歯後に一時的な炎症や腫れが見られる場合があります。必要に応じて投薬や専門医の診察を行います。下顎の親知らずの抜歯では感覚障害のリスクもあります。
18. 歯の形態修正・咬合調整
治療後に最適な咬合を得るため、歯の形を微調整したり、咬み合わせの調整を行う場合があります。
19. 装置の破損・誤飲
装置が破損したり、誤って飲み込んでしまうこともあります。異常に気づいたら速やかにご連絡ください。
20. エナメルクラックの発生
装置を外す際や強い力が加わった場合に、エナメル質に微細なヒビ(クラック)が入ることがあります。対応は状態により異なります。
21. 歯の後戻り
治療終了後にリテーナーを適切に使わない場合、歯が元の位置に戻る「後戻り」が起こることがあります。定期的なチェックが重要です。
22. 補綴治療・再治療の必要性
治療後、咬み合わせの変化に応じて補綴物(かぶせ物)や修復物の調整・再作製が必要になる場合があります。
23. 再治療の可能性
成長や加齢、歯周病の進行などによって歯並びが変化し、再治療が必要になることがあります。
24. 親知らずの影響による再移動
親知らずの萌出などにより、歯列に乱れが生じることがあります。必要に応じて対応します。
25. 加齢による咬合変化
加齢に伴い歯を支える骨が変化することで、咬み合わせが乱れることがあります。
26. 元の状態には戻せない
一度始めた矯正治療は、原則として以前の歯並びや咬合状態に戻すことはできません。方向性としては「改善を目指す治療」であることを前提に考えてください。
最後に
矯正歯科治療には多くのメリットがありますが、副作用や予期せぬ反応が完全に排除できるわけではありません。当院では、こうしたリスクに対しても真摯に対応し、状況に応じて適切な説明・対処を行うことを重視しています。
大切なのは、患者様と矯正歯科医が信頼関係を築いた上で、万が一のトラブルにも冷静に、そして丁寧に向き合うことです。経験と実績をもとに、少しでも安心して治療を受けていただけるよう努めておりますので、どうぞご不明な点はいつでもお気軽にご相談ください。